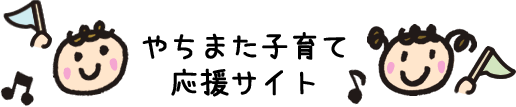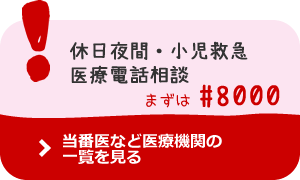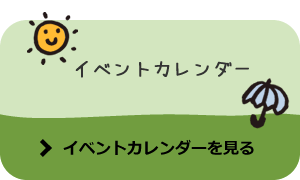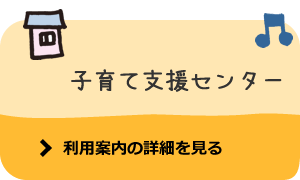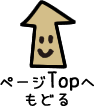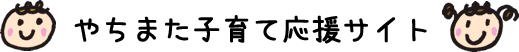本文
こどもの予防接種
予防接種とは
赤ちゃんはお母さんのおなかの中にいる時は胎盤を通して免疫をもらっています。
その免疫も次第に薄れていき、病気にかかりやすくなります。その病気から守ってくれるのが予防接種です。
病気の原因となるウイルスや細菌の毒性を弱めて作ったワクチンを体内に入れることによって、免疫を作って病気にかからないようにしたり、かかっても軽く済むようにしてくれます。
定期予防接種について
予防接種法に基づく定期の予防接種は下記のとおりです。
八街市が発行する予診票を使って、決められた接種期間に接種すれば公費(無料)で接種することができます。
また、定期予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
定期予防接種の種類と接種間隔
| 予防接種の種類 | 対象年齢 | 標準的接種期間および接種回数 | 備考 | ||||||||||||
| B型肝炎 | 1歳未満 | 27日以上の間隔で2回接種 1回目から139日以上の間隔をおいて3回目接種 |
初回接種2回分の予診票は出生届出時に、3回目の予診票は、4か月乳児相談時に予防接種手帳でお渡しします。 | ||||||||||||
| ヒブ | 生後2か月以上 5歳未満 |
【2か月以上7か月未満】 27日以上の間隔で初回接種3回(1歳未満) 初回接種終了後7か月以上あけて追加接種1回 |
令和6年4月1日より5種混合での接種になりました。 すでに、1回以上接種済みの方は引き続き接種可能です |
||||||||||||
| 小児用肺炎球菌 | 生後2か月以上 5歳未満 |
【2か月以上7か月未満】 27日以上の間隔で初回接種3回(2歳未満) 初回接種終了後60日以上あけて1歳以降に追加接種1回 |
初回接種3回分の予診票は出生届出時に、追加接種の予診票は、4か月乳児相談時に予防接種手帳でお渡しします。 | ||||||||||||
| 4種混合 (ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ) |
1期:生後2か月以上 7歳6か月未満 |
【2か月以上1歳未満】 20日以上の間隔で初回接種3回 初回接種終了後1年から1年6か月までの間隔(最短6か月)をあけて追加接種1回 |
令和6年4月1日より5種混合での接種になりました。 |
||||||||||||
| 5種混合 (ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ、ヒブ) |
1期:生後2か月以上 7歳6か月未満 |
【2か月以上1歳未満】 20日以上の間隔で初回接種3回 初回接種終了後1年から1年6か月までの間隔(最短6か月)をあけて追加接種1回 |
初回接種3回分の予診票は出生届出時に、追加接種の予診票は、4か月乳児相談時に予防接種手帳でお渡しします。 | ||||||||||||
| BCG | 1歳未満 | 生後5か月から8か月までに1回 | 予診票は、4か月乳児相談時に予防接種手帳でお渡しします。 | ||||||||||||
| 麻しん風しん混合 | 1期:1歳以上2歳未満 | 1歳を過ぎたらできるだけ早期に1回 | |||||||||||||
| 2期:小学校就学前 1年間(年長児) |
小学校入学前の1年間(4月1日~3月31日)に1回 | ||||||||||||||
| 水痘 | 1歳以上3歳未満 | 1歳を過ぎたらできるだけ早期に1回、6か月以上(最短3か月)の間隔で2回目を接種 | |||||||||||||
| 日本脳炎 | 1期:生後6か月以上 7歳6か月未満 |
【3歳から4歳までに】6日以上の間隔で2回初回接種終了後、概ね1年(最短6か月以上)の間隔をあけて追加接種1回 | |||||||||||||
| 2期:9歳以上 13歳未満 |
9歳以上10歳未満に1回 | 9歳のお誕生の翌月に予診票を郵送します。 | |||||||||||||
| 2種混合(ジフテリア、破傷風) | 11歳以上13歳未満 | 11歳以上12歳未満に1回 | 11歳のお誕生日の翌月に予診票を郵送します。 | ||||||||||||
| 子宮頸がん | 小学校6年生~ 高校1年生相当年齢にある女子 |
【1回目の接種が15歳以下】 |
中学1年生時に学校にて予診票を配布します。 |
||||||||||||
| ロタ | ロタリックス 生後2か月~生後24週0日 ロタテック 生後2か月~生後32週0日 ※どちらのワクチンも1回目は14週6日までに接種 |
ロタリックス |
予診票は出生届時に3枚お渡しします。 | ||||||||||||
定期予防接種のすすめ方
- 予防接種は、すべて医療機関での個別接種となります。原則予約ですが、一部予約なしで実施している医療機関もあります。
予約を入れる際には必ず、出生届け出時にお渡ししている「予防接種とこどもの健康」と「こどもの定期予防接種のご案内」をよく読み、体調のよい時に接種を進めましょう。 - 医療機関で接種の記録をしますので、必ず母子健康手帳をお持ちください。
- 予防接種には、父または母が必ず同伴してください。父・母でない方が同伴される際には、委任状が必要になります。 委任状 あるいは、規定の様式でなくても必要事項の記載(保護者の住所・直筆の署名・捺印、子どもの氏名、予防接種名、代理人の住所・氏名・続柄)で代用できます。
- それぞれの予防接種は、接種間隔が定められています。異なる種類の予防接種をする場合には、下記のようにあけてください。
- 予診票を紛失した場合は、母子健康手帳を持って、健康増進課で再発行の手続きをしてください。
- 詳しい感染症の情報は、国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト<外部リンク>でご確認ください
- 予防接種を受ける前のチェックポイント [PDFファイル/141KB]
- 委任状 [Excelファイル/15KB]
予診票について
- 出生届け出時に、B型肝炎(2枚)、ヒブ(3枚)、小児肺炎球菌(3枚)、5種混合(3枚)ロタ(3枚)をお渡しします。その他の予診票は、4か月乳児相談にお越しの際に、「予防接種手帳」でお渡しします。必ず4か月乳児相談にお越しください。
- 転入の方には、転入届け出時に母子健康手帳で接種歴を確認し、八街市の予診票をお渡しします。八街市の予診票がないと公費(無料)で受けられませんのでご注意ください。
予防接種の接種間隔
令和2年10月1日から異なるワクチンの接種間隔が変更になりました
→ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
- 同じ種類のワクチンを複数回接種する場合は、それぞれのワクチンに定められた接種間隔を守ってください。
- 2種類以上の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行う同時接種は、医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。
※注射生ワクチン:BCG、水痘、麻しん風しん混合、麻しん、風しん、おたふくかぜ
※経口生ワクチン:ロタ
※不活化ワクチン:5種混合、2種混合、不活化ポリオ、日本脳炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん、B型肝炎、季節性インフルエンザ
病気が治ったあと、予防接種をうけるまでの間隔
- 麻しん、風しん、水痘およびおたふくかぜ等にかかった場合には、身体が回復するのを待って接種しましょう。下記を目安にし、かかりつけの先生と相談しながらすすめてください。
- これらの病気にかかった方と接触し、潜伏期間内にある可能性が高い場合も、お子さんの様子をみせて、かかりつけの先生と相談しながら決めましょう。
| 麻しん | 治癒後4週間程度 | |||||||||
| 風しん、水痘、おたふくかぜ等 | 治癒後2~4週間程度 | |||||||||
| 突発性発疹、手足口病、伝染性紅斑等 | 治癒後1~2週間程度 | |||||||||
市内で定期予防接種ができる医療機関
令和7年度定期予防接種市内契約医療機関一覧 [PDFファイル/34KB]
八街市外の病院で接種するには
・八街市外の医療機関でも下記リンク「千葉県相互乗り入れ協力医療機関」の医師のもとであれば、八街市の予診票を使って公費(無料)で接種することができます。
→千葉県内定期予防接種相互乗り入れ協力医療機関<外部リンク>
・八街市は、予防接種センター(千葉県こども病院内)と契約しています。対象者はアレルギーを持っていて予防接種ができない人などの要注意者です。予防接種センターでの接種を希望する場合は、依頼書を作成しますので、八街市健康増進課までお越しください。該当になるか心配な方は事前に健康増進課にお問い合わせください。
→千葉県こども病院のご案内<外部リンク>
予防接種による健康被害救済制度について
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了するまたは障害が治癒する期間まで支給されます。ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の原因(予防接種をする前あるいは、後の紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものか因果関係を予防接種・感染症医療・法律等各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
→厚生労働省予防接種健康被害救済<外部リンク>
長期療養者等の定期接種の機会の確保について
接種対象年齢期間において、免疫機能に異常をきたす病気、免疫抑制をきたす治療が必要なもの、コントロール不良のてんかん、重症心不全、重症呼吸不全等の予防接種を受けることが適当でないもの、臓器移植等で予防接種不適当原因が生じ、接種期間が十分に確保できず、やむを得ないと認められた場合は、こうした原因が解消された日から2年以内は、定期の予防接種として接種できます。
上記の病気にかかっていたことや、やむを得ず定期接種を受けることができなかったと判断した理由等を医師が記載した診断書(長期療養者この当理由書)を予診票に添付すれば公費(無料)で受けられます。健康増進課にお問い合わせください。
下記の予防接種は受けられる年齢の上限が決まっているためご注意ください。
- 5種混合、4種混合は15歳に達するまで
- BCGは、4歳に達するまで
- Hibは、10歳に達するまで
- 小児肺炎球菌は、6歳に達するまで
日本脳炎予防接種についてのお知らせ
(予防接種法施行令の一部改正)平成23年5月20日施行日
特例対象者について
1.平成7年4月2日から平成19年4月1日に生まれた者で20歳未満にある者で日本脳炎の第1期・第2期を完了していない者は、19歳まで(20歳のお誕生日の前日が最終期限)公費(無料)で予防接種を受けることができます。
これは、平成17年の厚生労働省による日本脳炎予防接種の積極的な勧奨の差し控えの勧告により、接種機会を逃している方のための不足回数を補う措置です(日本脳炎の特例措置)。
この年代の方は、日本脳炎の接種状況に個人差がありますので、ご不明な点は、母子健康手帳をお持ちのうえ、健康増進課までお越しください。確認のうえ、八街市の予診票をお渡しいたします。
→日本脳炎の予防接種についてのご案内(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
海外渡航などに関する予防接種情報
予防接種のシステムは、各国の社会・経済的事情、医学的事情などにより大きく異なっており、また日本の予防接種のすすめ方が国際的に共通の方法というわけではありませんので、出国前に予防接種の準備が必要です。日程は少なくとも2~3か月前、できれば半年くらいの余裕を持って計画的に順序よく受けていくようにしましょう。
→厚生労働省検疫所ホームページ<外部リンク>
→(公財)日本検疫衛生協会<外部リンク>
→外務省ホームページ<外部リンク>